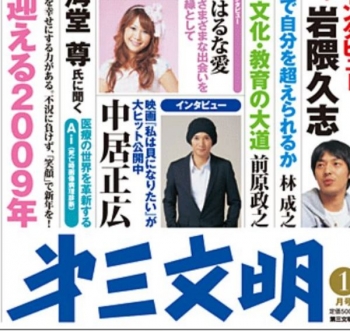.
プーチン大統領12月訪日 露補佐官「日本と合意」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160831-00000067-san-eurp
![newsプーチン大統領12月訪日 露補佐官「日本と合意」]()
【モスクワ=黒川信雄】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は30日、
プーチン大統領が12月に日本を訪問することで日本側と合意し、具体的な日程も決定済みだと述べた。インタファクス通信が伝えた。具体的な日程については、「日本側との合意を踏まえて公表する」と語った。
日本政府関係者によると安倍晋三首相は12月上旬、地元の山口県にプーチン氏を招き、首脳会談を行う。
ウシャコフ氏はまた、会談の議題など訪日の詳細については、9月2日に露極東ウラジオストクで予定される、日露首脳会談で話し合われる見通しだと述べた。
プーチン氏の訪日をめぐっては2014年2月、露南部ソチを訪れた安倍首相とプーチン氏が会談し、同年秋に実施することで合意したが、その後のロシアによるウクライナ南部クリミア半島併合などを受け、延期になった経緯がある。 その後、ロシア側はメドベージェフ首相ら要人が相次ぎ北方領土を訪問し、日本側が抗議。また、今年1月にはラブロフ露外相が日本との平和条約締結について、「領土問題の解決と同義ではない」と述べ、領土問題の存在を事実上否定するような発言をするなど、対立が深まっていた。
そうした中、安倍首相は5月に再びソチを訪問し首脳会談を実施。領土問題で双方が受け入れ可能な解決策を見いだすため、「新たな発想」に基づくアプローチで交渉を進めることを提案し、プーチン氏と合意していた。
◇
日本政府は30日、ロシアのプーチン大統領の12月来日が固まったことを「歓迎」(政府筋)する一方、両国間の最大懸案である北方領土交渉についてはロシア側の出方を注視しながら協議を進めていく。
日本側は、プーチン氏来日を「領土交渉前進への格好の機会」(政府関係者)と捉え、高官協議を続ける方針だ。安倍晋三首相の地元・山口県で首脳会談を行う予定であることについて、政府筋は「首相の強い意向の表れ」と指摘。外務省幹部は「くつろいだ雰囲気の中で話し合い、領土問題で目に見える成果につなげる」との狙いを語る。
ただ、北方領土交渉で日露首脳が合意した「新たな発想」に基づくアプローチについては、具体的な道筋が見えているわけではないのが現状だ。
政府部内には
「交渉進展にロシア側を引き込むのは容易ではない」(外務省筋)との慎重な見方も強い。
12月来日のプーチン氏、首相地元・山口で会談 安倍首相「節目の年」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160901-00000064-san-pol
![news12月来日のプーチン氏、首相地元・山口で会談 安倍首相「節目の年」]()
■領土交渉 率直な議論期待 あすウラジオで首脳会談
日露両政府は31日、プーチン大統領が今年12月上旬に来日し、安倍晋三首相の地元・山口県での首脳会談開催に向け本格的な調整に入った。
首相が地元で外国の首脳と会談するのは初めてとなる。プーチン氏を地元に招き、くつろいだ雰囲気の中で話し合うことで信頼関係をさらに緊密にし、領土交渉の進展につなげたい考えだ。 日本政府は31日、安倍首相が9月2、3両日にロシア極東のウラジオストクで開催される「東方経済フォーラム」に出席し、プーチン氏と2日に会談すると正式に発表した。詳細な来日日程や会談の議題などについて詰めの協議を行う。来日は1泊2日となる見通しで、会談場所は県内の旅館を軸に検討している。
首相は31日、鈴木宗男元衆院議員と官邸で会談し、ロシア側がプーチン氏の12月訪日を公表したことについて「向こうから言ってくれたのはありがたいメッセージだ。極めて好意的な話だ」と歓迎した。さらに、
12月に1956(昭和31)年の日ソ共同宣言発効から60周年を迎えることから、「大きな節目の年だ。しっかり取り組んでいきたい」と強調した。
菅義偉(すが・よしひで)官房長官は31日の記者会見で「新しいアプローチで交渉を精力的に進めることで一致している。率直な議論が行われることを期待する」と語った。
日本政府は、北方領土交渉の進展には、安倍首相と領土問題の最終的な決定権を持つとされるプーチン氏の直接対話が不可欠とし、首脳会談を重視。ロシアによるクリミア併合で制裁措置を実施した欧米などと足並みをそろえる一方で、ロシアとの対話の窓口を閉ざさないよう配慮してきた。それだけに、プーチン氏来日を「領土交渉前進への格好の機会」(政府関係者)と捉えている。
ただ、領土交渉をめぐる「新たな発想」に基づくアプローチの具体的な道筋は見えていない。日本政府内には交渉がロシアペースで進むことへの懸念もあり、外務省幹部は「どこまで進展するか予断を持って言えない。首相の判断次第だ」と指摘した。
<北方領土>ロシア人居住権を容認へ 政府方針
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160901-00000004-mai-pol
![news<北方領土>ロシア人居住権を容認へ 政府方針]()
政府は、
ロシアとの交渉で北方領土が日本に帰属するとの合意が実現すれば、既に北方領土で暮らすロシア人の居住権を容認すると提案する方針を固めた。5月の日露首脳会談では、領土交渉を進展させるために「新たなアプローチ」で臨むことで一致しており、今回の方針は新アプローチを具体化するものになる。歴史的経緯を巡って帰属を争う従来の協議が進展しなかった反省から、両国が合意した後の日本側の姿勢を示すことで、事態打開を図りたい考えだ。
安倍晋三首相は9月2日から2日間の日程でロシア極東ウラジオストクを訪問する。今回の方針に基づくロシア側との協議は、2日のプーチン大統領との会談や、2カ月に1回のペースで行っている外務次官級の平和条約締結交渉を想定している。ロシア側の検討を促し、12月に来日する予定のプーチン氏から前向きな姿勢を引き出す構えだ。
日本政府関係者によると、
ロシア側は5月以降、「新アプローチを提案した日本が具体案を提示すべきだ」との意向を伝えてきた。北方四島には現在、約1万7000人のロシア人が居住し、主に水産業や水産加工業に従事している。政府はロシア人の退去や両国による共同統治は困難とみて、日本に帰属した場合でもロシア人の待遇を一定程度保障する必要があると判断した。政府内には、より幅広く権利を保障し、高度な自治を維持する考えもある。これまでも政府は領土問題解決時にロシア人の「人権や利益、希望」を尊重する方針を示してきたが、居住権の容認を明確に示すことで、具体的な返還時期や条件などの協議進展につなげる狙いがある。
一方、首相は5月の首脳会談で、島民だった日本人の望郷の思いについて語っている。日本政府内では、両国が帰属問題で合意する場合には、ロシア側に元島民らの居住権を認めるよう要求し、日本人の移住を可能にする案もある。元島民らは現在、墓参や交流などを目的とする一時滞在のみ認められている。返還後のロシア人の権利容認の前例とする狙いだが、ロシアの実効支配を追認することにもなりかねず、政府内で異論が出る可能性もある。
北方領土を巡っては、「第二次世界大戦の結果、自国領になった」と主張するロシアと、「固有の領土」と訴える日本が対立し、協議が行き詰まってきた。首相が提案した「新アプローチ」は、日本への帰属などで合意したとの想定で、統治制度のあり方について検討を目指すものと言える。
ただ、ロシア側が領土問題でどこまで譲歩するかは不透明で、居住権だけでなく、住民自治や行政機構のあり方など詰めるべき点は多岐にわたる。私有地の登記やロシア企業の資産の扱い、学校教育のあり方などの難題も多く、日本の思惑通りに協議が進むかは未知数だ。【前田洋平】
和さん、情報ありがとうございます。
「北方領土を返還したとき、住んでるロシア人は
どうするんだ?」という話は前からあったわけだ
が、やはり残すようでつね。
まあ、返還されてロシア本土と自由に往来できな
くなるなり、商売するにも関税がかかり、物価も
税制も違う、言葉も通じないとなれば黙ってて
も出て行くでせう(縛w
で、プーチン来日。
こないだの会談の時もそうだったが、
ロシア側から食い気味に発表(縛w
詳細な日程は明日明後日の会談でとか(縛w
なぜネゴってから発表しない?(縛w
おそらく害務省のせんべい共がサボタージュ
してて、それを粉砕するためでつね。
日本を中心として米露が飛車角、なんざ
エ下劣とその下僕のせんべい共にとっては
悪夢でしかないでせうからな。
北方領土の密約をしたのはルーズベルト。
ルーズベルトといえばコノコフィリップス(縛w
コノコといえばサークル「K」(縛w
ルーズベルトと言えばニューディール、
ニューディールといえば武者小路(縛w
ルーズベルトとブッシュは遠めの血縁、
両者とも麻薬ビジネス、
全部つながってるわけでつね。
うちの記事を読んでわかる通り、そのスキームが
轟音と共に崩壊している真っ最中だということ
なんでつね。
わかり松。
( ゜∀゜)・∵ブハ八ノヽ/ \!!!!!!!!<おまけ>
かなり前の記事だが、ずっと出しどころを
探ってたもの。
ロシアはずいぶん経済が回復してるようで、
プーチンが「2年程度で」といってた通りに
なったわけでつね。
雨降って地固まったロシア経済、資源国の弱点克服
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160725-00047398-jbpressz-int
![news雨降って地固まったロシア経済、資源国の弱点克服]()
■ ロシアの景気後退は底打ち?
7月14日、IMF(国際通貨基金)はロシアの経済見通しを発表した。
2016年のGDP(国内総生産)成長率は貸出条件の厳格化と実質所得の減少、さらに国内投資の低迷を背景にマイナス1.2%と依然マイナス成長であるが、前回見通しのマイナス1.5%からは上方修正されている。
さらに
2017年については、金融緩和と国内需要の緩やかの回復を背景にプラス1.0%の成長を見込んでいる(図表1)。
しかも、この予測の前提となる原油価格(年平均)は2016年が42.2ドル、2017年が48.8ドルである。足許の原油価格の推移を見ると原油価格はこれらの予測値を上回って推移しており、GDP成長率もさらに上方修正される可能性もある。
実際、7月初にロシア連邦統計局が発表した2016年第1四半期のGDP成長率は前年同期比マイナス1.2%と市場予想よりも下落率は小幅にとどまった。
前回の拙稿(「世界唯一のインフレファイター、ロシア中銀総裁語る」)ではロシア政府当局による景気先行きへの強気な見方を紹介したが、ロシア経済に対して最も悲観的かつ批判的であるIMFすらも今回上方修正を行ったことに留意が必要だろう。
日本のメディアではいまだに「欧米諸国の経済制裁の影響によって経済が苦境にあるロシアでは・・・」という決まり文句がよく聞かれるが、そろそろ新たなフレーズを用意する必要がある。
ロシア経済が「底打ち」した理由はまず第1に原油価格の反発である。
さらにもう1つの理由を挙げるとすれば
経済構造がルーブル安に適合し始めた、つまりルーブル安を有利に使い始めたことだろうか。すなわち「輸入代替」の進展であり、この輸入代替の動きは農業と軽工業に顕著に見られる。
ロシアにおいては1998年、2008年と経済危機が起こり、ルーブルが急落するたびに輸入代替の動きが顕著に見られたのだが、今回の経済危機においてはこれまでの輸入代替とは異なる質的な変化があるように感じる。
■ 農業における輸入代替
ロシアには広大な農地があり本来であれば有力な農業生産国になるポテンシャルがあるはずである。モスクワから南部の地方都市へのフライトの際に飛行機の窓から眺めていると日本では考えられない規模の農地や温室農場を随所に見かける。
しかし、
原油高に支えられてルーブルが長い間高値を維持していたため、ロシア人は野菜、食肉などを自国で生産せずに諸外国から輸入する体制がすっかり定着してしまった。
こうした状況はクリミア紛争以降、ルーブル相場の急落と欧米諸国の経済制裁に対抗するロシア政府の食糧輸入禁輸措置によって変化を余儀なくされた。
もちろん、後者については欧米諸国以外からの輸入に代替すればいいのだが、ロシア政府は経済政策に加えて食糧安全保障の観点からも国内での食糧生産を積極的に支援するようになっている。
筆者は先日、モスクワから南方に車で2時間ほどのところにある野菜栽培の温室農場を見学する機会があった。この農場は2015年2月から造成を始め10か月で完成、現在は5ヘクタールの温室でキュウリを栽培している(下の写真)。
温室と言っても日本のビニールハウスとはその規模が大きく異なる。
鉄骨とガラスで組み立てられた温室は天井高が5~6メートルはあるだろうか、1つのユニットが1ヘクタールとのことで、反対側の壁がはっきり見えないくらいの巨大な温室である。 栽培技術はオランダから最先端の水耕栽培装置と技術を導入しており、通年での栽培が可能である。
この農場は今夏に規模を22ヘクタールまで拡張してトマト栽培を開始する計画で、造成工事が急ピッチで進められていた。農場の経営者によると、
同農場はロシアではまだ小規模な部類であり今後も規模拡大を計画しているという。
筆者は温室内で説明を受けながら、勧められるままにその場でもぎ取ったキュウリを試食させてもらった。品種はロシアでよく生食、あるいはピクルスにされる長さ10センチ程度のやや丸みを帯びたキュウリである。
説明によると温室内で使用する農薬は生物農薬なので洗わずそのまま食べても人体に害はないと言う。味に関しては同行したロシア人によれば「とてもおいしい」とのことであった。
筆者は農業の専門家ではないので、この農場に対する評価を加える立場にはないが、一ビジネスパーソンとして「こんなに巨大で儲かるのかな」という疑問だけが残った。というわけで農場の経営者にストレートに聞いてみたのだが、返事は「儲からないならやるわけないだろう」。
もっとも、ロシアでこうした巨大農場が設立されるのには合理的な背景がある。
1つはロシアの農業が株式会社化されていることである。1990年代は資源・エネルギーを中心とする国営企業の民営化(とその結果としてのオリガルヒの誕生)が中心であったが、2000年代に入って、それまで手つかずだった農業部門の民営化が進んだ。
ロシアの農業のポテンシャルに着目した内外の投資家たちが壊滅状態にあったソ連時代の集団農場(コルホーズ)や国営農場(ソホーズ)を底値で買い集め、株式会社化し、さらには上場させたケースがいくつもある。
上場企業であるということは、それだけ資金調達力があり大型化が可能であるということである。
もう1つはロシア政府による農業、特に温室野菜栽培に対する補助金の存在である。
筆者は具体的な法令までは確認していないのだが、関係者に聞いたところでは温室の建設費用の4割近くは政府からの補助金で賄われているという。
この制度を利用して近年は多くの大手農業会社、あるいは投資グループがロシア各地に数十ヘクタール規模の温室農場の建設に乗り出しているという。
こうした農業の輸入代替がロシアの食品加工分野にも好影響を及ぼしていることはモスクワ市内のスーパーの棚を見ると明らかである。肉製品、乳製品を中心に従来のヨーロッパからの輸入品に代わってロシア製の加工食品が並んでいる。
ここ数年はワインすら国産品が棚の一角を占めており、市内の高級レストランでもワインリストにロシア産ワインが加えられるようになった。価格はロシアにおけるチリ・南ア・グルジアワインと概ね同じレベルである。
■ ファッションにおける輸入代替
さて次に筆者が気になるのは分野は繊維業界、と言うよりもファッション業界である。ルーブル下落前は欧米の有名ファッションブランドにとってロシアは上客であった。
もちろんこれらのブランドの多くは今でもモスクワ市内に店を構えているのだが、かつてのような賑わいは感じられない。その一方で、ロシア人のデザインによる、ロシア国内で生産されたファッションブランドを街中でよく見かけるようになった。
最近、筆者が街中で見かけた例を挙げてみよう。
市内の高級ショッピングセンターで見つけた「ザポロージェッツ・ヘリテージ」は若者向けカジュアルウエアのブランドである(右の写真)。
「ザポロージェッツ」とはソ連を代表する国産小型車で粗悪品の代名詞である一方、庶民にとっては親しみ深い車である。それをあえてブランドにするのもひねりが利いていて面白い。
また市内の中心部にブティックを構える「グランジ・ジョン・オーケストラ・エクスプロージョン」は、名前こそ英語名であるが製品のラベルには「メイド・イン・ロシア、モスクワの某所で製造」と書かれている。
同ブランドはアディダスとのコラボ・モデルなども発表する実力派で、市内の高級デパートでも取り扱われている。
価格はTシャツが8000~1万円と決して安くはないが若者中心に人気のようである。ロシア製でもそれだけ製品のデザイン・品質が上がっており、それだけのお金を支払う消費者が存在するということだろう。
足許のロシア経済は、民間消費の回復の遅れが景気回復の足かせとなっている。
消費の低迷はもちろん実質所得の減少によるところが大きいのだが、ルーブル安や経済制裁によって一度は高品質の輸入品に親しんだロシアの消費者のニーズを満たす製品が存在しなくなったことも要因の1つとも考えられる。
現在進行中の輸入代替が、ロシア国内の「量」の需要を満たすだけでなく、「質」の需要も満たすようになれば国内消費の回復ペースも早まるのではないだろうか。